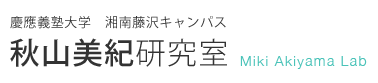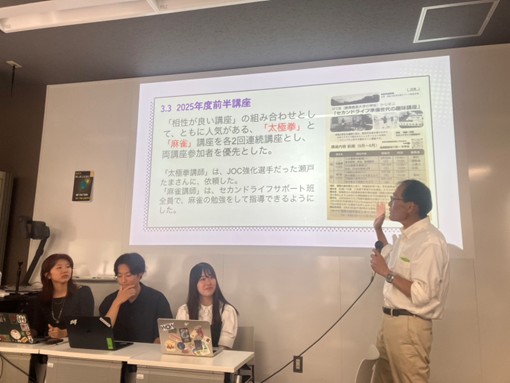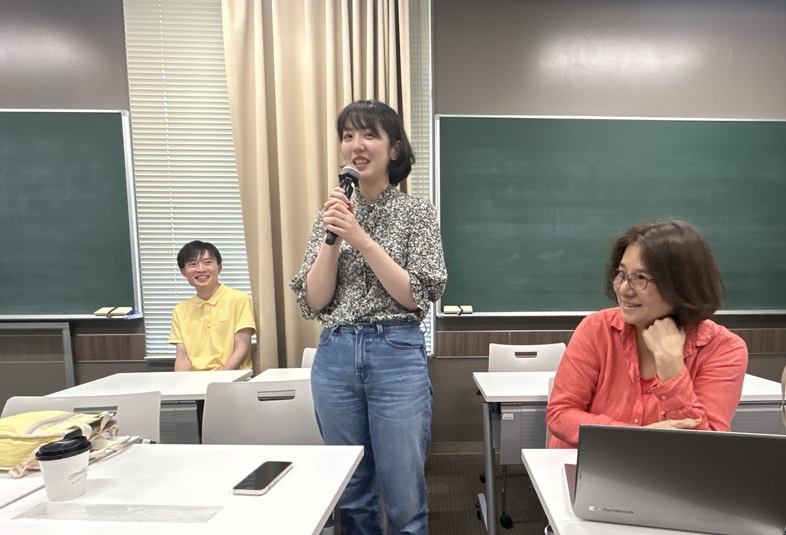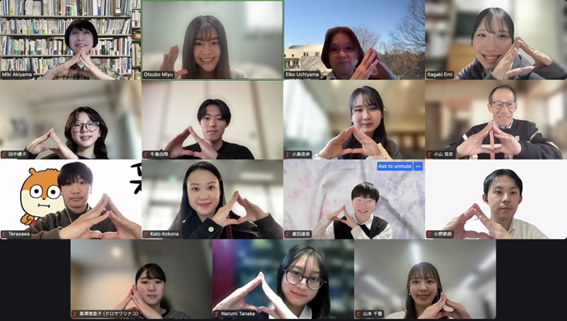2025.05.28
5限 【マイプロ発表と各班での活動】
こんにちは!総合政策学部3年の小山浩史です。
今日の5限の授業では、最初に3年生の学生一人が、マイプロ発表を行いました。
テーマは、「文化的背景と生活環境が及ぼす睡眠への影響とその実態」でした。
発表の中で、日本の学生は世界的に見て睡眠時間が短いことや、睡眠時間や睡眠の質が、文化的な背景(日本人は睡眠時間を減らして努力するのが美徳という考えなど)や生活環境(通勤通学時間など)からどのような影響を受けるかといった興味深い内容でした。
マイプロ発表の後は、「セカンドライフサポート班(高齢者のコミュニティ作りに関する活動)」「つなぐ班(骨髄バンクに関する活動)」「チルドレンケアラー班(長期療養児童へのサポートに関する活動)」「健康ゲーム班(認知症に関する活動)」「居場所班(子供の居場所に関する活動)」の五つの班に分かれて活動を行いました。
私が所属するセカンドライフサポート班では、6月から湘南大庭地区センターで開催する「セカンドライフ世代の趣味講座」の参加者に記入して頂くアンケート内容について、議論しました。質問文についても、高圧的な表現にならないようにするにはどう表現すれば良いかを、ChatGPTも利用しながら検討しました。特に今年度は、参加者同士のコミュニティが継続的に成り立つために、麻雀サークルを立ち上げることを目標としており、地域の皆様がワクワクする楽しい場となるように準備を進めています。